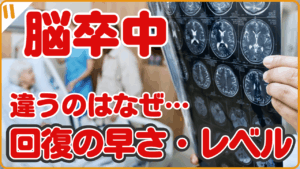【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する④】運動再学習を邪魔する要因3選
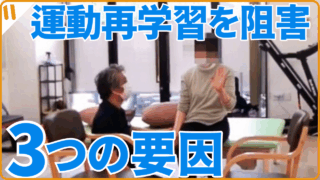
【ポイント・まとめ】
■前提
・脳卒中発症の急性期~回復期初期を想定して解説
・シナプス可塑性は誰にでもあり、再学習や回復は可能
・ただし、脳卒中で脳細胞が壊死している場合、完全な回復は難しい
・運動学習は可能だが限界があり、人によって回復度合いは異なる
■運動再学習を阻害する3つの要因
①高次脳機能障害
1-1.遂行機能障害と脱抑制
・脳が圧迫される事により、前頭前野と小脳の連携トラブルから生じる
・「物事の認識」や「意味づけ」「目的理解」など、人間らしい高度な精神機能に支障が生じる
・目の前の課題をどうすればよいか分からない
・イライラや怒りっぽくなり感情の抑制ができない(脱抑制)
・行動や動作の意味が理解できず、練習にならない
1-2.反側空間無視
・身体の片側半分の空間を認識できない
・指示は理解しても、身体をどう動かせばよいかが分からない
1-3.失語症
・相手の言っていることが分からない
・自分の気持ちや考えを伝えられない
・思考や状況判断ができず混乱し、指示にも反応しにくい
②体調の悪化・廃用性
・誤嚥性肺炎、褥瘡、再発、転倒骨折など
・医療的処置が優先され、リハビリが中断される
・脳の可塑性が高い「黄金の3ヶ月」を有効利用できなくなる
・長期で寝たきりになると、麻痺が重く見えるが、実は動かせる場合もある
・対応策としては、病状が軽快した瞬間を狙って、少しでも練習を始めること
③うつ傾向
・「うつ病」とまではいかないが、やる気が出ず自己肯定感が下がっている状態
・原因は「脳卒中」という生命に関わる大きなストレスとなる
・ストレス耐性は個人差がある
・回復には生活リズムの安定が重要(同じ時間での起床、食事、リハビリ)
・ルーチン化された生活で脳の負荷を下げ、やる気や思考の余力を取り戻す
回復を促す考え方
・①~③に共通:ワーキングメモリ(作業記憶)に支障をきたしている
・運動学習には「できた」「良くなった」という実感が必要
・病的要因によりこの記憶・認識がうまく働かず、学習が定着しないケースもある
・ハードル(課題レベル)を患者に合わせて目標設定する
・遂行機能障害:簡単で意味が分かりやすい課題を
・うつ傾向:やや難しめの課題で達成感を与えることが有効な場合も
・日常リズムを整えて、ストレスの少ない環境で継続的にリハビリを行うのが効果的
動画内容・チャプター
0:17 シナプス可塑性は誰にでもある(前回復習)
0:53 運動再学習を邪魔する要因
1:21 ゆ子さんコメント・回復は性格次第
3:40 入院中に運動学習を阻害する病的な状態
4:26 阻害要因① 高次脳機能障害
5:06 1-1.脱抑制と遂行機能障害僕は
5:39 脳の内圧亢進による前頭前野への影響
10:16 1-2.半側空間無視
11:10 1-3.失語症・コミュニケーション障害
14:54 阻害要因② 体調悪化
16:12 臥床の長期化による廃用性
17:26 阻害要因③うつ傾向
19:13 日常生活のリズムが大切
20:24 共通点:ワーキングメモリーに障害が出る
24:08 手足の練習が十分にできず麻痺が重篤に見える
25:09 急性期~1ヶ月位:個人に合った課題設定